取材日記
イタリア研修日記【4】~パンフォルテなど(スパイス考察)~

スパイスの利いたお菓子から十字軍へ想いをはせる
イタリアのみならず、ヨーロッパ各地には、伝統的に「スパイスをよく利かせたお菓子」というものがあります。
フランスのパンデピス、ドイツのレープ・クーヘンや北欧のジンジャークッキー(ペッパーカーカなど)などなど。
これらの起源は11世紀の「十字軍遠征」に由来するようです。
大航海時代に「黒胡椒が金と等価で交換された」なんて話、聞いたことありますよね。
モノの価値というものは相対的なものなんだな(希少とあらば値がどんどん高騰する)と思ったものですが、十字軍遠征で西欧に持ち帰られたスパイス類はやはりその希少性と特徴的な香りと、さらには薬効まで期待できるということで大変もてはやされた、のだと思います(このあたりは想像を楽しんでください(笑))
特別な日にスパイスのお菓子
それだけ人気と希少性のあったスパイスを、せめてクリスマスなどの特別な日に楽しもうよ、ということでヨーロッパ各地で伝統菓子が発達していきました。
シナモンやクローブ、コショウにカルダモンなど、今では1年を通して身近に手に入るこれらのスパイスを、当時はとても味わい深く楽しんでいたのだろうなと想像します。
フィレンツェやシエナなどのトスカーナ州でも「パンフォルテ」や「パンペパート」など、ハチミツやドライフルーツとスパイスを混ぜて固めた(ヌガーのような)お菓子が親しまれています。
これらも少し地域が違うと呼び名や使用するスパイス、スタイルが変化します。
でもすみません、私はそこまで詳しくないので(正直者)イタリアで実際に体験した話に戻ります。

スパイスのお菓子を真剣に学ぼう
留学時代は「なんか古めかしいお菓子だなぁ。スパイス効いてるんだなぁ」くらいであまり深く追わなかった私。
反省の弁はひとまず脇に置くとして、「イタリア人にとっての“スパイス菓子”とは、どのような味わい(香り)のものなのか」を改めて真剣に学び取りたいと思ったことが、今回の視察の目的の一つでもありました。
以下はその感想です。
このジャンルも「もっと美味しくなるのでは」と思うお菓子です(笑。
(そんなことばかり言ってる気がします)
スパイスって「香り」と思いがちですが、実は「味」にも強く作用します(香りが味に影響する、のではなく、スパイスの持つ味がつく、と私は思っています)。
だから「スパイスはこれくらいね」っていうのは「塩はこんくらい」っていうのと一緒。
塩加減って重要ですよね。同じくらい「どれだけ使うか」が繊細な分野じゃないかとあらためて思いました。

パンペパートとよく似ていますが、こちらには胡椒が入っておらず
子供でも食べられるお味。
分量や比率…さらに掘り下げるスパイスのお菓子
「このお菓子はスパイスを効かせるものよ」で思考を停止してしまうと、そこから先に向上はしません。
どのスパイスがどれだけ入って欲しいのか、この比率でいいのか、などが作り手の腕の見せ所だと思います。
そのスパイスの起源や効能、他にどんな親しまれ方をしているかなど掘っていくと、深みにはまっていくかも知れないですね(笑)。
でもなぁ、パンフォルテのジェラートとか、開発したいよなぁ。。
スパイスのお菓子:ビナーシェのラインナップ
ビナーシェでも今は「黒糖&クルミ」「黒糖&落花生(千葉県限定)」でシナモンを使用しています。
黒糖との相乗効果を狙いつつ「シナモン味にはしない」ところを狙うのは、むしろ塩加減より微妙なラインかもしれません。
今回の視察では新しく他のスパイスの魅力も知れたので、今後のお菓子作りに反映させていきたいと思います。
コメント
 コメントをする
コメントをする
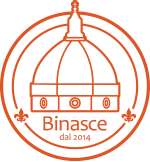

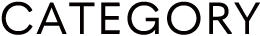
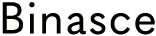





コメントはまだありません。