取材日記
イタリア研修日記【5】~「ジトっとしたお菓子」たち~

マカロンはお好きですか?
みなさんは「マカロン」はお好きですか?
私の世代(40代)が子供の頃、ああいったお菓子はまったく見ることがありませんでした。
今では「高級なフランスのお菓子」としてだいぶ浸透しているような気がします。
もう一度訊くのですが、マカロンはお好きですか?

マカロンの奥深さと「ジトっとした」食感
マカロンの主材料はメレンゲ、アーモンドプードル、砂糖と、いたってシンプルです。
シンプルだけれども奥が深いお菓子で、「間にクリームをはさむ」ことで一大革命が起き、現在の形に至りました。
なぜ2度も「お好きかどうか」をお聞きしたかというと、あの「ジトっとした」食感は、日本ではあまり例えようがなく、苦手な人もいるのでは?と思ったからです。
日本はどちらかと言えば「キレのある」甘さを追究していたように思います。
イタリアの「ジト系」お菓子
そんな「ジト系」のお菓子ですが、フランスと同じヨーロッパのイタリアにも、もちろんたくさん存在します。
今回私が食べた中でも、「リッチャレッリ」「ブルッティ・マ・ブオーニ」「アマレッティ・ディ・モデナ」など、本当に色々あるんですね。
イタリアのお菓子は「しっかり甘くて美味しい」タイプのお菓子たちです。
(話が脱線しますが、昔テレビを見ていたら「甘くなくて美味しい」なんていう食レポをする人がいました。そういうの聞くと「そんなわけないだろ、『甘さがちょうどよくて美味しい』んだろ!と思わずテレビにツッコんでしまいます 笑)
和菓子との違い
よく言われることですが、和食はみりんや砂糖等”料理に甘みを使う”分、デザートの甘さは控えめ、イタリアは”料理に甘味を使わない”分、デザートはしっかり甘くする傾向にあるようです。
またこれらイタリアの「ジト系」お菓子では「メレンゲ」が活躍します。
卵白を泡立てただけのシンプルな素材ですが、そのわりに和食・和菓子でメレンゲを使う技法はあまり発達していません。(卵白を使う技法はあるのですが、メレンゲとなると伝統的な日本食ではあまり使われていないと思います。)
あれだけ一つの素材に対して掘り下げまくって引き出しまくってありとあらゆる方面の食べ物に昇華する日本なのに、この点は不思議です(お米や大豆を例にすると比べ物にならないですよね)。
これは私の考えですが、きっと「ガスの普及」※が影響しているはずです。
江戸時代、鎖国により産業の発達が欧米と異なった日本では、ガスを燃料とする技術の導入が遅れました。
オーブンやコンロなどの調理熱源の発明や普及も遅れ、それをベースとした調理技法の発達が中世においてはあまり無かったのだと思います。
もしオーブンが江戸時代に導入されていたら、どんな食文化が生まれていたのでしょうか。

今回の視察では、この「ジト系」の美味しさも改めて感じることができました。
一歩バランスを間違えると「甘っ!!」と日本人に拒絶されかねないこれらのジト系お菓子。
しかし日本にこれだけマカロンが広まったことを考えると、きっとまだまだ広がる土壌はあると思っています。

※編集者注:
メレンゲは、ガスが普及する前の17世紀に既に考案されていた技法です。
そのため、ガスの普及がメレンゲの調理技法の発達にどの程度影響を与えたかについては、分かりませんし、明確な資料もありません。
しかし、メレンゲのような「泡立て」や「均一に焼く」といった、経験や体力を必要とする難しい技法が普及するために、ガスオーブンや電気器具など、新しいエネルギーの導入が大きな影響を与えたことは確かです。
なぜ日本でメレンゲのような技法が発展しなかったのかについて、正確な考察は歴史家に任せるべきでしょう。ここではあくまで筆者の個人的な意見としてご覧いただければ幸いです。
石窯オーブン、薪と石炭、対流熱と反射熱で「均一に熱を加え」「カリッと焼き上げる」欧州
かまど、薪と炭、直火、蒸気で「下から局所的に熱を加え」「ふっくら蒸し上げる」日本。
調理技法がそれぞれ独自に発展していったことは興味深いですね。
編集者S
コメント
 コメントをする
コメントをする
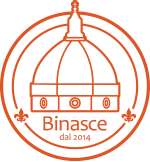

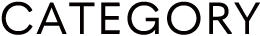
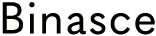





コメントはまだありません。